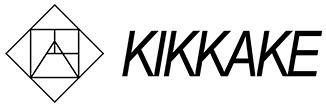「せっかくお金をかけて動画を作ったのに、誰にも見られていない…」
「かっこいい映像だけど、結局売上にはつながらなかった…」
そんな“動画制作後あるある”に、心当たりはありませんか?
実は多くの企業が、「作る」ことにフォーカスしすぎて
「使い倒す」視点が抜け落ちているのです。
特に、採用動画・サービス紹介動画・SNSプロモーション動画など、
あらゆる場面で動画ニーズが高まっている今、
“活用前提の動画戦略”がなければ成果には直結しません。
本記事では、動画を「作って終わり」にしないための
実践的なマーケティング活用法を、
映像制作会社がマーケター視点で深掘りします。
【このような方におすすめ】
- 映像制作を検討中の経営者・広報・採用担当者
- 過去に動画を作ったが、思った効果が出なかった方
- 「動画って効果あるの?」と疑問を持っているマーケ担当者
1. なぜ“動画は作るだけでは意味がない”のか?

動画は「制作して納品された瞬間」がゴールではありません。
むしろ、そこからどう活用されるかがROIを左右する本番です。
例えば、
・SNSで1回だけ投稿して放置
・Webサイトに埋め込んだけど告知せず
・営業部が活用方法を知らない
こうした状態では、いくら映像の質が高くても
「効果の見えない動画」になってしまいます。
動画は“使って初めて資産”です。
届け方・使い方を設計することが最も重要なのです。
むしろ、そこからどう活用されるかがROIを左右する本番です。
例えば、
・SNSで1回だけ投稿して放置
・Webサイトに埋め込んだけど告知せず
・営業部が活用方法を知らない
こうした状態では、いくら映像の質が高くても
「効果の見えない動画」になってしまいます。
動画は“使って初めて資産”です。
届け方・使い方を設計することが最も重要なのです。
2. 動画活用マーケティングとは?3つの重要視点

どんな時も動画が必要になった理由は存在します。
制作中に忘れていくこともありますが、動画を活用すると考えた時に最も効果がでるのが、その理由だということはよくあります。
そんな「動画が必要だ!」となった理由を思い出すための視点を紹介します。
視点①:目的の明確化
認知を広げたいのか
商品理解を深めたいのか
コンバージョンを促したいのか
採用応募を増やしたいのか
これが曖昧なままだと、効果的な映像は作れません。
“目的→構成→使用先”の順で設計しましょう。
視点②:使用チャネルの決定
チャネル(活用先)は動画設計の土台です。
たとえば、
SNS広告で拡散を狙うか
サイトのTOPでファーストビューにするか
展示会でループ再生するか
チャネルに最適化した内容・尺・フォーマットで作ることが、活用成功の鍵になります。
視点③:“1本で終わらせない”発想
動画は1本で終わらせず、
15秒版に切り出し
サムネイルテストでAB検証
メルマガに挿入
営業資料に添付
など、複数の導線へ再利用する前提で作りましょう。
制作中に忘れていくこともありますが、動画を活用すると考えた時に最も効果がでるのが、その理由だということはよくあります。
そんな「動画が必要だ!」となった理由を思い出すための視点を紹介します。
視点①:目的の明確化
認知を広げたいのか
商品理解を深めたいのか
コンバージョンを促したいのか
採用応募を増やしたいのか
これが曖昧なままだと、効果的な映像は作れません。
“目的→構成→使用先”の順で設計しましょう。
視点②:使用チャネルの決定
チャネル(活用先)は動画設計の土台です。
たとえば、
SNS広告で拡散を狙うか
サイトのTOPでファーストビューにするか
展示会でループ再生するか
チャネルに最適化した内容・尺・フォーマットで作ることが、活用成功の鍵になります。
視点③:“1本で終わらせない”発想
動画は1本で終わらせず、
15秒版に切り出し
サムネイルテストでAB検証
メルマガに挿入
営業資料に添付
など、複数の導線へ再利用する前提で作りましょう。
3. 目的別:動画の活用戦略と配信チャネル設計

| 目的 | 活用チャネル例 |
|---|---|
| 認知拡大 | Instagramリール、YouTube Shorts、X広告など |
| 商品理解促進 | Webサイト・営業資料・展示会ブースなど |
| 採用 | 採用LP、求人媒体動画枠、会社説明会 |
| 商談支援 | 見積書添付、プレゼン動画、事例紹介動画 |
| エンゲージ強化 | 社内報、メルマガ、定期YouTube更新など |
チャネル設計は“動画の使い道”そのもの。
設計なき動画は、誰にも見られない可能性が高くなります。
動画を作ることになった目的を再度思い出してみてください。
4. 動画マーケティングの成功事例

▶ 事例①:BtoB製造業A社
製品紹介動画を営業資料に埋め込み。
商談の成約率が28%アップ。
少し複雑な説明もアニメーションでわかりやすく制作。
▶ 事例②:美容サービス業B社
ショートドラマ広告をTikTokに展開し、
3週間でフォロワー+200名/CV率1.8倍を記録。
▶ 事例③:中小IT企業C社
採用動画をWantedlyに掲載。
動画なしの月に比べ、応募数が3倍に増加。
製品紹介動画を営業資料に埋め込み。
商談の成約率が28%アップ。
少し複雑な説明もアニメーションでわかりやすく制作。
▶ 事例②:美容サービス業B社
ショートドラマ広告をTikTokに展開し、
3週間でフォロワー+200名/CV率1.8倍を記録。
▶ 事例③:中小IT企業C社
採用動画をWantedlyに掲載。
動画なしの月に比べ、応募数が3倍に増加。
5. 活用効果を最大化するために必要な4つの準備

何度も言いますが動画は「作る」だけでは成果に直結しません。
本当に効果を発揮させるには、企画段階から活用までを見据えた設計が重要です。
ここでは、動画制作で成果を出すための4つのポイントをご紹介します。
少し難しい用語も出てきますが、わかりやすく噛み砕いて解説を進めていきます。
________________
1. ターゲット設定(ペルソナ)
動画の成否を分けるのは「誰に届けるか」です。
ターゲットを明確にするために、ペルソナ(Persona)を設定します。
ペルソナとは、年齢・性別・職業・価値観・課題などを細かく設定した「架空の理想顧客像」です。
たとえば同じ企業紹介動画でも、
採用向け → 働く雰囲気や社員の声を重視
商談向け → 商品やサービスの実績・メリットを強調
と、訴求ポイントは大きく異なります。
誰に届けたいのかを明確にすることで、メッセージはより響く映像になります。
________________
2. KPIの設計
動画の効果を正しく測るためには、KPI(重要業績評価指標)を設計する必要があります。
KPIとは、最終的な目標に到達するまでの過程を数値で評価するための指標です。
動画活用でよく使われるKPIの例:
再生数:動画がどれだけ見られたか
CV率(コンバージョン率):視聴者が問い合わせ・応募などの行動に移った割合
LP回遊率:動画経由でランディングページに来た人が、どの程度サイト内を回遊したか
重要なのは、「再生数が多い=成功」とは限らないということです。
目的(売上増加、応募数増加など)に直結する指標を設定し、それを追いかけることが成果への近道です。
________________
3. 活用場面の洗い出し
制作前に「動画をどこで使うか」を明確にしておきましょう。
主な活用例:
展示会:ブースでループ再生し、来場者の目を引く
SNS:短い編集版をInstagramやTikTokで発信
営業現場:商談時にタブレットで再生して説明補助
求人ページ:働く様子を伝えて応募意欲を高める
制作段階から「複数の場面で使い回せる構成」にしておくことで、長尺版・短尺版・静止画切り出しなど、さまざまな形で展開でき、費用対効果が大きく向上します。
________________
4. 運用体制の構築
動画は公開して終わりではありません。継続的に活用し、改善するための体制づくりが重要です。
事前に決めておくべきポイント:
活用担当者:配信・効果測定を行う人
配信スケジュール:いつ・どの媒体で発信するか
改善PDCA:Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)のサイクルでブラッシュアップ
この運用体制がないと、「せっかく作った動画が一度きりで終わる」という事態になりかねません。
効果を最大化するためには、作った後の動き方まで視野に入れることが不可欠です。
本当に効果を発揮させるには、企画段階から活用までを見据えた設計が重要です。
ここでは、動画制作で成果を出すための4つのポイントをご紹介します。
少し難しい用語も出てきますが、わかりやすく噛み砕いて解説を進めていきます。
________________
1. ターゲット設定(ペルソナ)
動画の成否を分けるのは「誰に届けるか」です。
ターゲットを明確にするために、ペルソナ(Persona)を設定します。
ペルソナとは、年齢・性別・職業・価値観・課題などを細かく設定した「架空の理想顧客像」です。
たとえば同じ企業紹介動画でも、
採用向け → 働く雰囲気や社員の声を重視
商談向け → 商品やサービスの実績・メリットを強調
と、訴求ポイントは大きく異なります。
誰に届けたいのかを明確にすることで、メッセージはより響く映像になります。
________________
2. KPIの設計
動画の効果を正しく測るためには、KPI(重要業績評価指標)を設計する必要があります。
KPIとは、最終的な目標に到達するまでの過程を数値で評価するための指標です。
動画活用でよく使われるKPIの例:
再生数:動画がどれだけ見られたか
CV率(コンバージョン率):視聴者が問い合わせ・応募などの行動に移った割合
LP回遊率:動画経由でランディングページに来た人が、どの程度サイト内を回遊したか
重要なのは、「再生数が多い=成功」とは限らないということです。
目的(売上増加、応募数増加など)に直結する指標を設定し、それを追いかけることが成果への近道です。
________________
3. 活用場面の洗い出し
制作前に「動画をどこで使うか」を明確にしておきましょう。
主な活用例:
展示会:ブースでループ再生し、来場者の目を引く
SNS:短い編集版をInstagramやTikTokで発信
営業現場:商談時にタブレットで再生して説明補助
求人ページ:働く様子を伝えて応募意欲を高める
制作段階から「複数の場面で使い回せる構成」にしておくことで、長尺版・短尺版・静止画切り出しなど、さまざまな形で展開でき、費用対効果が大きく向上します。
________________
4. 運用体制の構築
動画は公開して終わりではありません。継続的に活用し、改善するための体制づくりが重要です。
事前に決めておくべきポイント:
活用担当者:配信・効果測定を行う人
配信スケジュール:いつ・どの媒体で発信するか
改善PDCA:Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)のサイクルでブラッシュアップ
この運用体制がないと、「せっかく作った動画が一度きりで終わる」という事態になりかねません。
効果を最大化するためには、作った後の動き方まで視野に入れることが不可欠です。
6. 「動画制作会社」に求められる役割も変化している

❌ 昔:映像の“かっこよさ”だけを追求
✅ 今:成果に直結する“活用戦略”まで設計
このように現代の企業は、単なる制作代行ではなく
「一緒に考えてくれるパートナー」を求めています。
・マーケティング視点を持っているか
・媒体別に適切な提案ができるか
・制作後の伴走も可能か
こうした点を重視して、制作会社を選定しましょう。
✅ 今:成果に直結する“活用戦略”まで設計
このように現代の企業は、単なる制作代行ではなく
「一緒に考えてくれるパートナー」を求めています。
・マーケティング視点を持っているか
・媒体別に適切な提案ができるか
・制作後の伴走も可能か
こうした点を重視して、制作会社を選定しましょう。
7. まとめ:制作=スタートライン。活用設計こそ本質

動画は作って終わりではなく、“使って成果を出す”ためのものです。
・目的を明確にし
・活用チャネルを選び
・配信・運用体制を構築し
・効果検証でブラッシュアップを重ねる
この流れを設計することこそ、動画マーケティングの本質です。
私たち「合同会社キッカケ」では、
動画制作の段階から“成果につなげる活用方法”をセットでご提案しています。
・SNS、LP、営業資料などの活用導線も設計
・二次活用を前提にした構成案をご提案
・制作後の配信までワンストップ対応
まずはお気軽にご相談ください!
少しでも気になった方はCONTACTからどうぞ!
・目的を明確にし
・活用チャネルを選び
・配信・運用体制を構築し
・効果検証でブラッシュアップを重ねる
この流れを設計することこそ、動画マーケティングの本質です。
私たち「合同会社キッカケ」では、
動画制作の段階から“成果につなげる活用方法”をセットでご提案しています。
・SNS、LP、営業資料などの活用導線も設計
・二次活用を前提にした構成案をご提案
・制作後の配信までワンストップ対応
まずはお気軽にご相談ください!
少しでも気になった方はCONTACTからどうぞ!